歴代総理大臣、将軍に並び、天皇についても、高校入試でも頻出する人物名のテーマです。今回は、入試に頻出する天皇をまとめています。また、現在の日本国憲法における天皇の国事行為についてもまとめています。
よく出る歴代天皇
飛鳥時代の天皇
- 推古天皇(すいこてんのう)…日本で最初の女帝(女性の天皇のこと)。聖徳太子を摂政とし、聖徳太子は、①十七条の憲法を定める。②冠位十二階を定める。③遣隋使を中国に送る。④世界最古の木造建築物である法隆寺を建築する。
- 天智天皇(てんじてんのう)…もとは中大兄皇子。つまり645年に大化の改新を行った人物である。①663年に朝鮮半島へ出兵し、唐と新羅の連合軍と白村江の戦いを行う。②その後、九州の防護のために防人を配置する。③天智天皇の跡継ぎ争いが壬申の乱と呼ばれる。
- 持統天皇(じとうてんのう)…女帝で、日本最古の貨幣である富本銭を作る。
奈良時代の天皇
- 聖武天皇(しょうむてんのう)…①743年墾田永年私財法を定める。②全国に国分寺・国分尼寺を建てる。③奈良に東大寺を建てる。④遣唐使がもって帰った宝物などを収めた建物である正倉院は聖武天皇のものだった。
平安時代
- 桓武天皇(かんむてんのう)…794年に平安京に遷都(都を移すこと)する。
- 白河上皇(しらかわじょうこう)…1086年に院政を始める。自ら「上皇」という位につき、天皇に代わって政治を行う政策。
- 後白河天皇(ごしらかわてんのう)…1156年の保元の乱で崇徳上皇と争う。
鎌倉時代の天皇
- 後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)…1221年に承久の乱を起こし、幕府をつぶそうとする。→その後、朝廷の監視施設である六波羅探題を京都に設置される。
南北朝時代の天皇
- 後醍醐天皇(ごだいごてんのう)…1334年に建武の新政を行う。後醍醐天皇は南朝で、奈良県の吉野で政治を行った。
天皇陛下の国事行為
天皇陛下の国事行為についても、入試では頻出します。どんな場面で天皇陛下が出現するのか、どの仕事において、任命、任免、公布などの行為を行うのか把握しておく必要があります。天皇陛下は、内閣の助言と承認により、国民のために、憲法の定める国事に関する行為を行います。
<具体例>
- 国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命すること
- 内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命すること
- 国務大臣その他の官吏の任免を認証すること
- 国会を召集すること(国会開会式への臨席)
- 法律や条約を公布すること
- 憲法改正を公布
- 衆議院解散(判例では実質的解散権は内閣にあるとする。つまりは、形式的な解散の承認というレベルなのでは?)
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること
- 栄典を授与すること
- 大使の信任状を認証すること
- 外国の大公使を接受すること
など
天皇の存在
- 憲法第1条…「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とされています。
- 憲法第3条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」

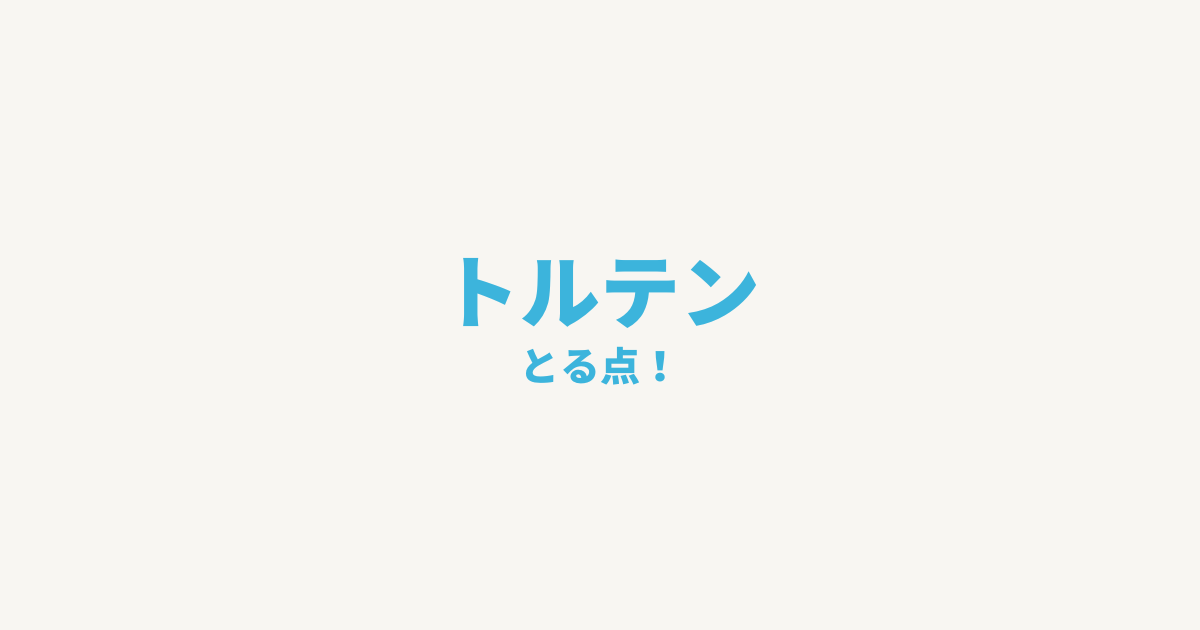
コメント