今回は、数ある年号のうち、覚えておきたい年号に加え、時代区分をまとめています。出来事の年号を聞かれる問題は少ないものの、出来事の年号の並び替えや同じ時代区分の出来事を選ぶなどそういう問題を解く際には、歴史の流れを知っておく必要があります。時代区分としては、大きな分け方として、古代・中世・近世・近代・現代となります。次のような区分にわけて、覚えておきたい年号をまとめていきます。
古代
古墳時代~平安時代院政期までです。
飛鳥時代
- 538 仏教日本に伝わる。
- 593 聖徳太子が摂政になる。
- 604 十七条憲法を制定。
- 607 小野妹子ら遣隋使派遣。
- 645 大化の改新。
奈良時代
- 701 大宝律令の制定
- 743 墾田永年私財法。開墾した(自分で耕した)土地であれば、永遠に自分ものにできる法律。
平安時代
- 794 桓武天皇が平安京に遷都
- 894 遣唐使を廃止する。
中世
平安時代院政期~戦国時代です。
平安時代
- 1086 白河上皇の院政始まる
- 1185 壇ノ浦の戦いで平家滅亡⇒守護・地頭の設置
鎌倉時代
- 1221 承久の乱、六波羅探題(後鳥羽上皇)
- 1232 御成敗式目(北条泰時
- 1274 文永の役(フビライハンVS北条時宗)
- 1281 弘安の役(フビライハンVS北条時宗)
- 1297 永仁の徳政令
- 1333 鎌倉幕府の滅亡(足利尊氏・新田義貞)
室町時代
- 1392 南北朝統一
- 1404 勘合貿易はじまる
- 1428 正長の土一揆…高利貸しを農民たちがおそいました。
- 1485 山城の国一揆
- 1488 加賀の一向一揆…浄土真宗の信者が守護を追い出して約100年の自治を行いました。
戦国時代
- 1467 応仁の乱
- 1543 鉄砲伝わる
- 1549 キリスト教伝わる
近世
安土桃山時代~ペリー来航までです。
江戸時代
- 1615 武家諸法度ができる
- 1637 島原の乱
- 1649 慶安の御触書
- 1709 新井白石の政治
- 1716 享保の改革。(徳川吉宗)
- 1772 田沼意次の政治
- 1787 寛政の改革(松平定信)
- 1825 外国船打払令
- 1837 大塩平八郎の乱
- 1841 天保の改革(水野忠邦)
近代
ペリー来航~第2次世界大戦敗戦までです。
江戸時代
- 1858 日米修好通商条約締結
- 1860 桜田門外の変⇒井伊直弼暗殺
- 1862 坂下門外の変⇒安藤信生負傷
- 1863 薩英戦争(鹿児島vsイギリス)
- 1866 薩長同盟成立⇒坂本竜馬が仲介を行う
- 1867 江戸幕府(徳川幕府)、大政奉還へ
明治時代
- 1868 五か条の御誓文、鳥羽・伏見の戦い
- 1869 版籍奉還
- 1871 廃藩置県・岩倉具視の欧米使節団
- 1872 学制(義務教育の開始)・鉄道
- 1873 地租改正・徴兵令・太陽暦
- 1874 民選議院設立建白書(板垣退助)
- 1877 西南戦争・地租が2.5%に
- 1881 国会開設の勅諭、自由党(板垣退助)
- 1882 立憲改進党ができる(大隈重信)
- 1884 秩父事件(埼玉県、自由民権運動の暴発〉
- 1885 内閣制度(伊藤博文)
- 1886 ノルマントン号事件
- 1889 大日本帝国憲法(伊藤博文)
- 1890 第1回帝国議会、教育勅語
- 1894 治外法権の廃止(陸奥宗光)・日清戦争
- 1895 下関条約(伊藤博文・陸奥宗光)三国干渉
- 1899 義和団事件
- 1901 八幡製鉄所の操業開始
- 1902 日英同盟
- 1904 日露戦争
- 1905 ポーツマス条約(小村寿太郎)
- 1910 韓国併合、大逆事件(幸徳秋水処刑)
- 1911 関税自主権回復(小村寿太郎)、辛亥革命
大正時代
- 1914 第一次世界大戦
- 1915 二十一ヶ条の要求
- 1918 シベリア出兵・米騒動
- 1923 関東大震災
- 1925 普通選挙法・治安維持法
昭和時代
- 1929 世界恐慌
- 1931 満州事変
- 1933 国際連盟脱退
- 1937 日中戦争
- 1939 第二次世界大戦
- 1941 太平洋戦争
- 1945 ポツダム宣言受諾
現代(戦後~)
- 1950 朝鮮戦争
- 1951 サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約
- 1956 日ソ共同宣言・国連加盟
- 1972 沖縄の復帰
- 1973 石油危機(オイルショック)
- 1978 日中平和友好条約
- 1990 東西ドイツ統一
- 1991 湾岸戦争・ソ連解体

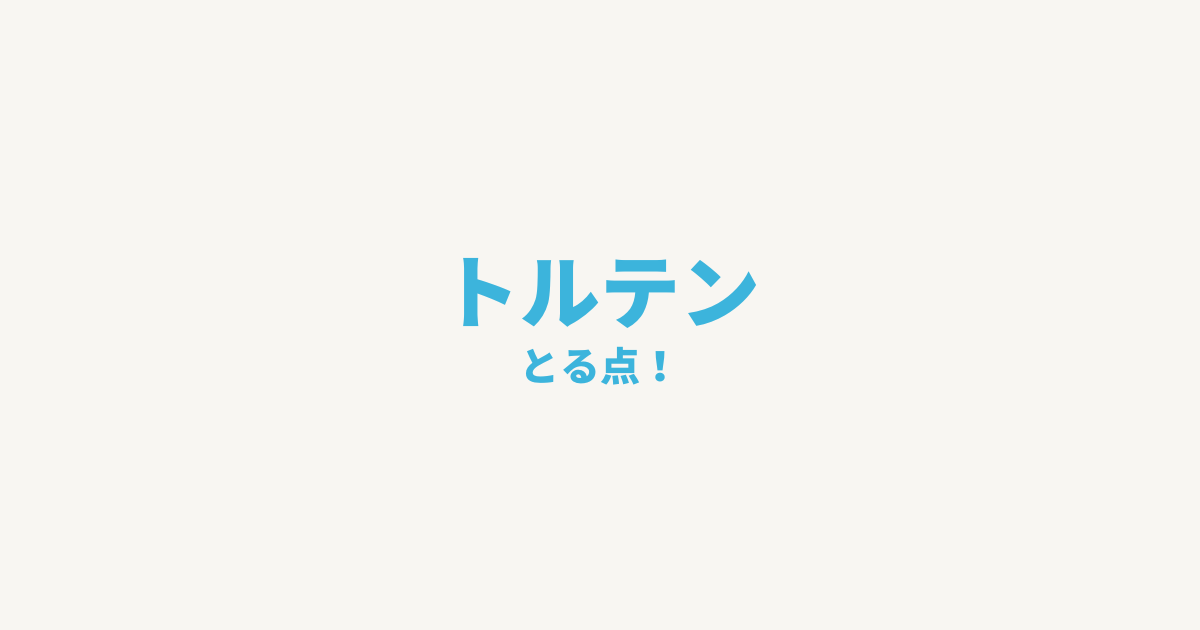
コメント